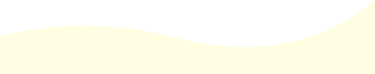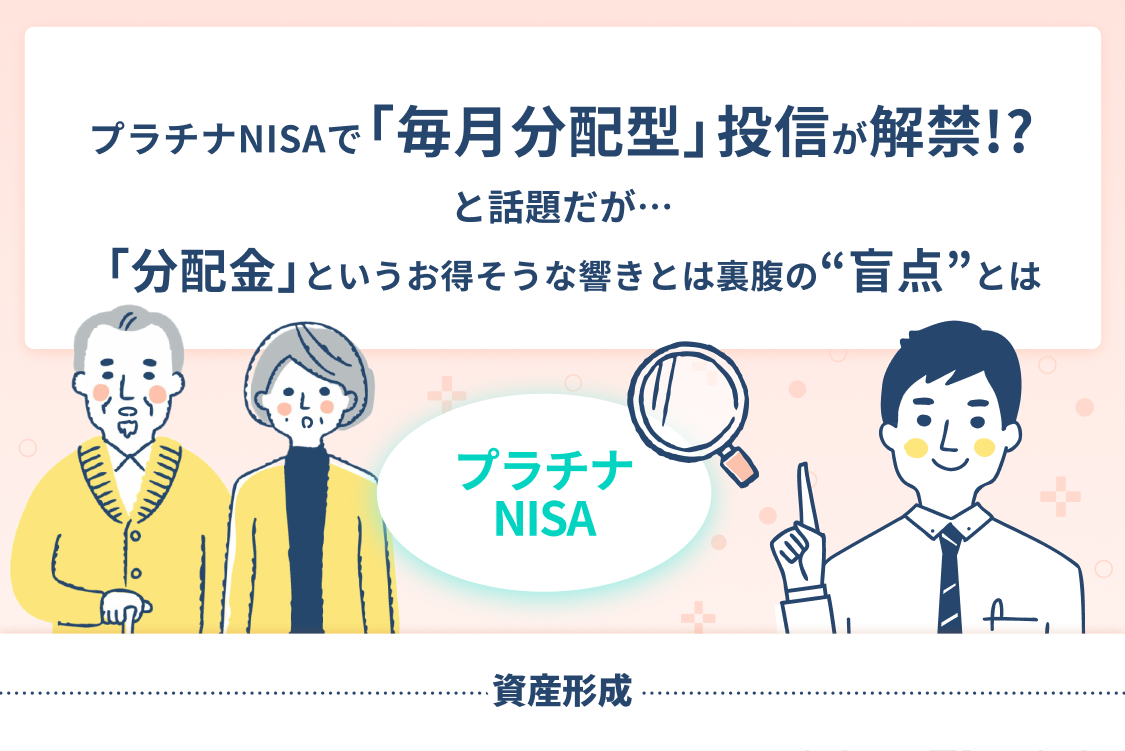
記事提供:Finasee(フィナシー)


プラチナNISAとは、高齢者を対象にしたNISAのことで、岸田前総理大臣が昨年11月に設立した資産運用立国議員連盟の提言書に、その創設が盛り込まれました。まだ提言書の段階ではありますが、4月16日付日本経済新聞朝刊によると、金融庁が2026年度の税制改正要望に盛り込む方針と記されています。
同記事には、プラチナNISAの具体的な内容が記されています。
というものです。
毎月分配型投資信託は現在、成長投資枠でもつみたて投資枠でも購入できません。なぜなら、現行NISAが資産形成層を対象にして、長期的な財産づくりを前提にした制度と考えられているからです。逆の見方をすると、毎月分配型投資信託は、長期の資産形成には不向きであると考えられています。
なぜ毎月分配型投資信託が、長期的な資産形成に向かないのか。いくつか理由があります。
大体、この2点に集約されると思います。投資信託の分配金は、「分配対象額」といって、「配当等収益」、「有価証券売買等利益」、「分配準備積立金」、「収益調整金」の4つを合計した額から、運用会社が分配方針、分配対象額の水準、基準価額の水準、市場環境などを総合的に勘案して決めます。そして分配金の額が決まったら、ファンドに組み入れられている株式や債券などの有価証券の一部を売却して現金化し、分配金として受益者に支払うのです。
ただ、組入有価証券の一部を売却すれば、運用会社は売却を仲介してくれた証券会社等の金融機関に、所定の売買手数料を支払わなければなりません。当然、分配回数が多いほどそのコスト負担は重くなると考えられますが、通常、多くの投資信託が年1~2回の分配回数であるのに対し、毎月分配型投資信託は年12回の分配金支払いがありますから、その分だけ組入有価証券の売買コストが割高になると考えられます。
また、一定の運用期間中に得られた運用収益を全額投資に回すことなく、取り崩していく形になるため、運用効率が悪くなります。
これらは1~2年程度の運用期間であれば、それほど表面化しませんが、10年、20年となると、リターンに大きな影響を及ぼすと考えられます。そのため、毎月分配型投資信託は長期の資産形成に不適格であり、NISAの対象から外されているのです。
では、なぜそれを今、高齢者対象とはいえNISAで買えるようにするというアイデアが浮上してきたのでしょうか。
高齢者といえば、すでに資産形成は終わり、それをいかに活用していくかというのが主目的になります。いわゆる資産活用です。65歳以上になると概ね退職し、定期収入は公的年金が中心です。
とはいえ昨今では、公的年金だけでは心許ないという声は多く、だからこそ6年ほど前に「老後2000万円問題」が大炎上したわけですが、分配金や売却益を非課税にできるNISAの対象に毎月分配型投資信託を組み込めば、その心許ない公的年金を多少なりともカバーでき、公的年金に対する不安・不満を払拭できるのではないか、という当局の算段が透けて見えるような気がします。
加えて言うなら、NISAの口座数増・残高増も期待できそうです。2025年4月3日に金融庁が発表した資料によると、世代別のNISA口座開設状況は、2024年9月末時点では以下のようになっています。
さらに上記の数字を、2024年10月1日現在の人口推計を用いて、各世代別のNISA口座開設率を計算してみます。
このように30歳代、40歳代、50歳代、60歳代が一山をつくり、70歳代以降は下がっています。
さすがに70歳代、80歳代以上の人たちに対して「さあ、これからNISAで資産形成をしましょう」などと呼びかけたところで、響かないのは当たり前。そこで、「毎月分配型投資信託で運用しながら取り崩して、資産寿命を先延ばしにしましょう」とアピールすれば、NISA口座の開設率が低い世代の関心が高まり、NISAの口座数や買付額が増えるかもしれないという、政策当局側の考えもあるのかも知れません。
では、毎月分配型投資信託は、運用商品として優れた特性を持っているのでしょうか。
かつて毎月分配型と言えば、国内外の債券に組み入れるタイプが中心でした。しかし近年では、海外株式を主要投資対象としたうえで、毎月分配を行うタイプが人気を集めています。
あるファンドを例に考えてみましょう。
このファンドはMSCIワールドインデックスをベンチマークにしたアクティブファンドで、新興国を除く世界中の株式に分散投資します。為替ヘッジをしないタイプの毎月の分配金は、1万口あたり150円です。それも、直近の運用報告書で確認できる、過去30期分がすべて150円なのです。結果、年間の収益分配金合計額は1800円になり、これを2024年1月23日の基準価額である9146円で買ったとすると、分配金の利回りは19.68%にもなります。
「いや、凄い。こんな利回りで運用できるなら、もう老後の生活は安泰だ」と思った人は、ほぼ間違いなく、数年後に後悔するはずです。
よく考えてみて下さい。皆さんは、収益分配金の主な原資は、基本的に前回決算の翌営業日から今決算日までの運用で得られた株式の配当金、債券の利金、それぞれのキャピタルゲイン、ならびに海外資産で運用するファンドなら為替差益だと思っていませんか。これが大きな誤解です。
もしそうだとしたら、株式などという値動きの不安定なものを組み入れて運用しているのに、どうして毎月の分配金が一定なのでしょうか。
運用報告書に記載されている「分配原資の内訳」に、この謎の答えが書いてあります。
当期分配金150円のうち、当期の収益が「-」で示されている期があります。これは、当期の運用で収益が得られなかったか、もしくはマイナスだったことを示しています。この期の分配金は、「当期の収益以外」で150円が支払われています。当期の収益が9円の期には、当期の収益以外で140円、当期の収益が99円の時は、当期の収益以外が50円だったりもします。ちなみに必ずしも150円にならないのは、小数点以下の処理の関係であるとされています。
では、「当期の収益以外」とは何なのでしょうか。
2つあります。「分配準備積立金」と「収益調整金」がそれです。
分配準備積立金は、分配されずにファンド内に留保された収益の設定来の累積であり、収益調整金は追加設定時に既存の受益者が本来受け取るべき分配金額が希薄化されてしまうのを防ぐために設けられた勘定のことです。
それぞれの中身を細かく説明すると、かなりややこしくなるので、いずれも現在の基準価額に含まれている過去からの収益金と考えて下さい。
つまり、「当期の収益以外」の部分から分配金の多くが支払われ続けると、たとえファンドの組入資産が値上がりしたとしても、基準価額には絶えず下落圧力がかかることになります。
ちなみに同ファンドの場合、ベンチマークであるMSCIワールドインデックスは、2022年7月25日から2024年12月23日までの間に約64%上昇している一方、分配金を支払った後の基準価額の上昇率は4.03%です。もちろん30期分の分配金を加味した基準価額で計算すると、54.71%の上昇率にはなりますが、残念ながらそれでもベンチマークには約10%近く負けています。
良いか悪いかはともかくとして、毎月分配型投資信託にはこういう特性を持ったものが多いということを、利用者は理解しておかなければなりません。
そして、最後に取って付けたような話で恐縮ですが、プラチナNISAで検討されているスイッチングは賛成です。できればプラチナNISAだけでなく、すべてのNISA口座開設者に、スイッチングを提供してもらいたいと思います。
※本コラムは、2025年4月公開当時の制度に基づいた内容です

有限会社JOYnt代表。1989年、岡三証券に入社後、公社債新聞社の記者に転じ、投資信託業界を中心に取材。1992年に金融データシステムに入社。投資信託のデータベースを駆使し、マネー雑誌などで執筆活動を展開。2004年に独立。出版プロデュースを中心に、映像コンテンツや音声コンテンツの制作に関わる。