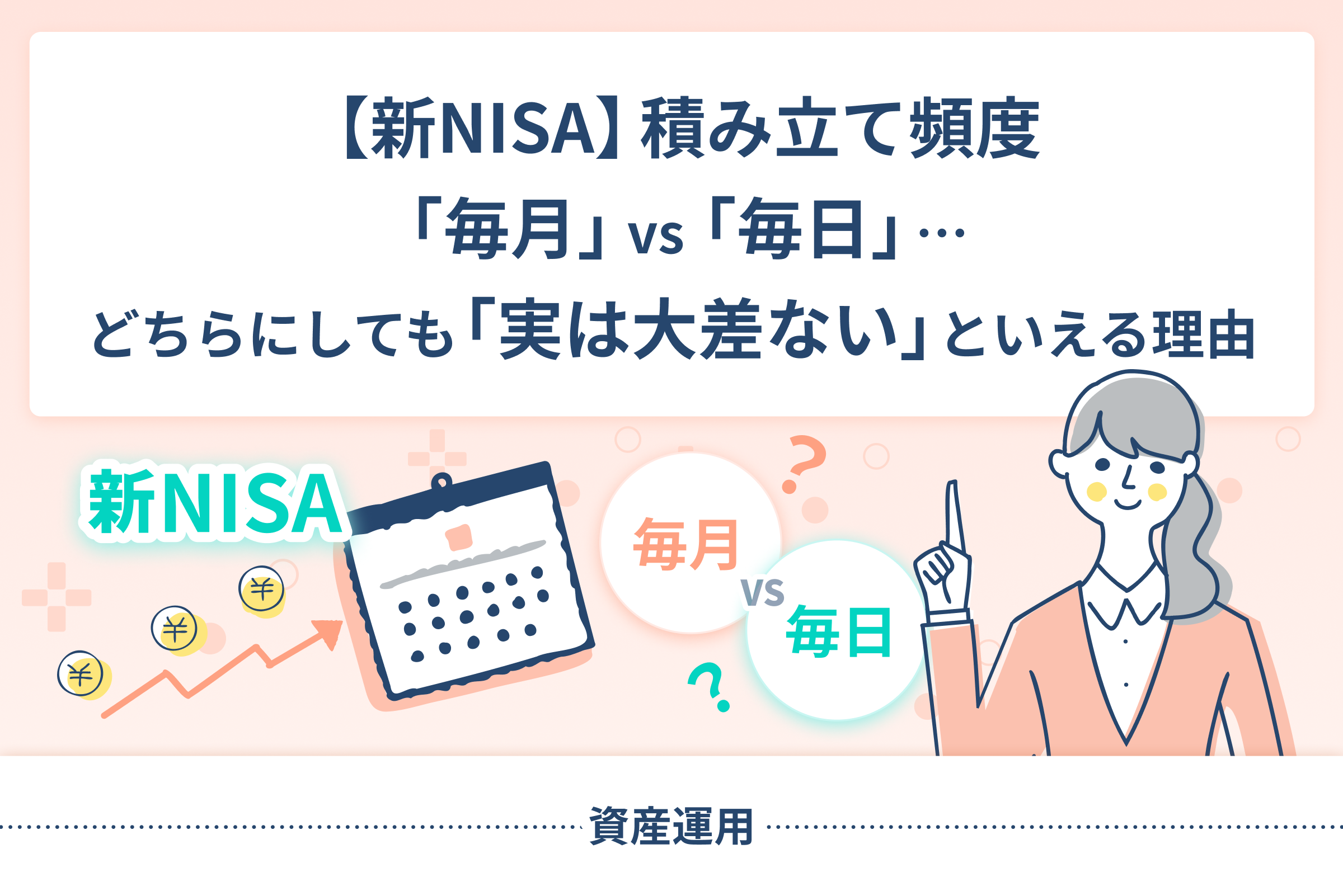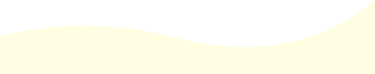2024年、ついに新NISAがスタートした。その直前である2023-2024年の年末年始、ファンドアナリスト篠田尚子氏は新NISAにまつわる「質問攻め」にあったという。その中でも多くの人が疑問を持つであろう5つの質問をピックアップし、解説をしてもらった。
既に資産形成に取り組んでいる読者の中には、年末年始、NISA制度について友人や家族から相談を受けたという人も多かったのではないだろうか。筆者もご多分に漏れず、十数年ぶりに会った友人から行きつけのレストランのスタッフに至るまで、ありとあらゆる場面で質問攻めにあった。11年前の一般NISA、7年前のつみたてNISA開始時とは比較にならないほど、新NISAの認知度がじわじわと高まっていることを実感した。
そこで今回は、新NISAの開始に際し、筆者の元に寄せられた数々の疑問や質問から、特に多かった内容を一問一答形式でご紹介する。
記事提供:Finasee(フィナシー)


このページの目次
1日でも早く始めた方がいい?
質問「SNSや各種メディアを見ていると、新NISAはすぐに始めないといけないような印象を受けます。まだあまり理解できていないので、もう少し勉強してから始めたいのですが……」
回答
1日単位で焦る必要はなし。
新NISAは生涯利用できる制度に生まれ変わったので、当座の生活資金を確保し、制度について一定程度理解してから始めても決して遅くはありません。ただ、目標を決めておかないと、ずるずると先延ばしになってしまう可能性があります。ざっくりと、「1年以内」、「基本給が上がったら」といった目標を立て、「新NISAデビュー」に向けた準備をすることをおすすめします。
なお、「当座の生活資金」のめやすは、安定的な収入がある会社員の方なら月給の6カ月程度と考えておくとよいでしょう。
証券会社に万が一のことがあっても大
丈夫?
質問「個別株やETFの取り扱いがある証券会社を選んだ方がよいと聞きますが、これまで全く取引をしたことがなくて不安です。昔、経営破たんした証券会社もありますが、万が一そうなってしまった場合、お金はどうなるのでしょうか?」
回答
万が一証券会社が破たんしても、預けたお金がなくなることはない。
証券会社が投資家から預かっている株式、債券、投資信託などの有価証券は、証券会社が破たんしても確実に投資家に戻るように、自社の資産とは区分して管理することが法律で義務付けられています。これを「顧客資産の分別管理」と言います。
万が一、何らかの理由で証券会社が分別管理の義務違反をした場合は、証券業界で作る「日本投資者保護基金」が1人あたり1000万円を上限に補償することになっています。これを「投資者保護基金制度」と言います。なお、1998年の日本投資者保護基金の設立以降、実際に顧客に対して補償を行ったのは2例で、直近は、2012年に経営破たんした丸大証券(本社:東京都)でした。同社は、経営破たんに陥った際、顧客から預かった資金を分別管理せずに使い込んでいたことが発覚し、基金が顧客資産の補償を決めました。
このように、個人投資家が証券会社に預けている資産は、二重のセーフティーネットによって守られています。
新NISAの商品は「お墨付き」と考えて
いい?
質問「新NISAの商品は、金融庁が選んでいると聞きました。つまりは、優良な成績を収めている商品が選出されていると考えてもよいのでしょうか?」
回答
「お墨付き」が与えられているのではなく、投資初心者が円滑に資産形成を始め、継続できるよう、一定の基準が設けられているに過ぎない。
新NISAの対象商品は、投資信託の運用を担う運用会社が自ら届出を行ったものを、社団法人投資信託協会が取りまとめて公表しています。金融庁は、NISAの監督官庁として、対象商品の「基準」を作成しているに過ぎず、また、投資信託協会も、個別の投資信託の良しあしを判断しているわけではありません。
したがって、各投資信託が安定した成績を収め、長期にわたって投資家の支持を集められるかどうかは、あくまでも運用会社の手腕にかかっています。その点でも、商品について一定の知識を備え、自分が納得して付き合える商品を選ぶことが重要と言えます。
旧NISAでもうかっている投資信託は売
却してもいい?
質問「コロナ禍でNISA口座を開設し、以後3年ほど積立を続けてきました。旧NISAはいずれ終了すると聞きましたが、保有商品は売却した方がいいのでしょうか?」
回答
つみたてNISAを含む旧制度で購入した投資信託の非課税期間はいずれ終わりを迎える。含み益が発生しているなら解約し、新NISAの原資として活用するのもあり。
旧制度の一般NISAは投資をした各年から数えて5年、つみたてNISAは同20年間、非課税で運用を継続できます。つまり、制度の最終年にあたる2023年の購入分は、一般NISAで最長2027年まで、つみたてNISAで同2042年まで非課税で商品を保有し続けられます。いずれの場合も、まだ非課税で継続保有できる期間に猶予はありますが、いずれは終了するため、おおむね20%以上の含み益が発生している場合は解約(売却)し、新NISAの投資原資に充ててもよいでしょう。
なお投資信託は、全額はもちろん、保有資産の半分だけ、含み益に該当する額だけなど、部分的に解約することも可能です。
積み立てる頻度は「毎月」よりも「毎
日」にした方がいい?
質問「旧NISAでは毎月1日に3万円を積み立てていましたが、SNSなどを見ると、毎日数百円程度、貯金箱にお金を入れるように積み立てている人も多いようです。やはり、月1回よりも回数を増やした方が分散効果はあるのでしょうか?」
回答
積立投資の購入頻度を増やしても、平均買付単価を引き下げる効果は限定的で、最終的なリターンに大きな差は生まれない。
一見すると、積み立てる頻度を増やした方が、より時間分散効果が高まるように感じられますが、現実にはリターンに大きな差は生まれません。これは、積立投資における平均買付単価が、一般的な算術平均ではなく、「調和平均」によって求められるためです。
「調和平均」とは、いわゆる「平均」の一種で、往復の平均速度などを算出する際に用います。一般的な算術平均が、対象となるデータ値を足してデータ数で割るのに対し、調和平均は、対象となるデータの逆数を足してデータ数で割り、さらにその逆数を取るという方法で算出されます。投資信託の基準価額は、「1万口あたりの評価額」なので、平均買付単価を求める際は、算術平均ではなく、この調和平均を使います。
例えば、1万口あたりの基準価額が当月1万円、翌月1万3000円、翌々月1万2000円の投資信託を積み立てた場合、平均買付単価はいわゆる一般的な算術平均(対象となるデータ値を足してデータ数で割る)の1万1667円ではなく、1万1527円になります。
調和平均には、算術平均よりも値が小さくなるという特徴があるほか、データ数が多くても、そのデータ群の散らばり度合によっては、一定の値に収束するという性質があります。投資信託の基準価額は不規則に変動するため、購入回数を増やしても、平均買付単価にさほど影響が表れないのです。
「毎日積立」を選ぶこと自体を否定はしませんが、投資効果に過度な期待をしないこと。あくまでも、「気持ちの問題」程度に思っておいたほうがよいでしょう。
※本コラムは、公開当時の制度に基づいた内容になっており、今回の公開あたり一部修正しております。
 執筆者
執筆者
篠田 尚子(しのだ しょうこ)楽天証券資産づくり研究所 副所長 兼 ファンドアナリスト
慶應義塾大学卒業後、国内銀行を経て2006年ロイター・ジャパン入社。傘下の投資信託評価機関リッパーにて、投信業界の分析レポート執筆、評価分析などの業務に従事。2013年、楽天証券経済研究所入所。日本には数少ないファンドアナリストとして、評価分析業務の他、資産形成セミナーの講師も務めるなど投資教育にも積極的に取り組む。近著に『【2024年新制度対応版】NISA&iDeCo完全ガイド』『FP&投資信託のプロが教える新NISA完全ガイド』(ともにSBクリエイティブ)。